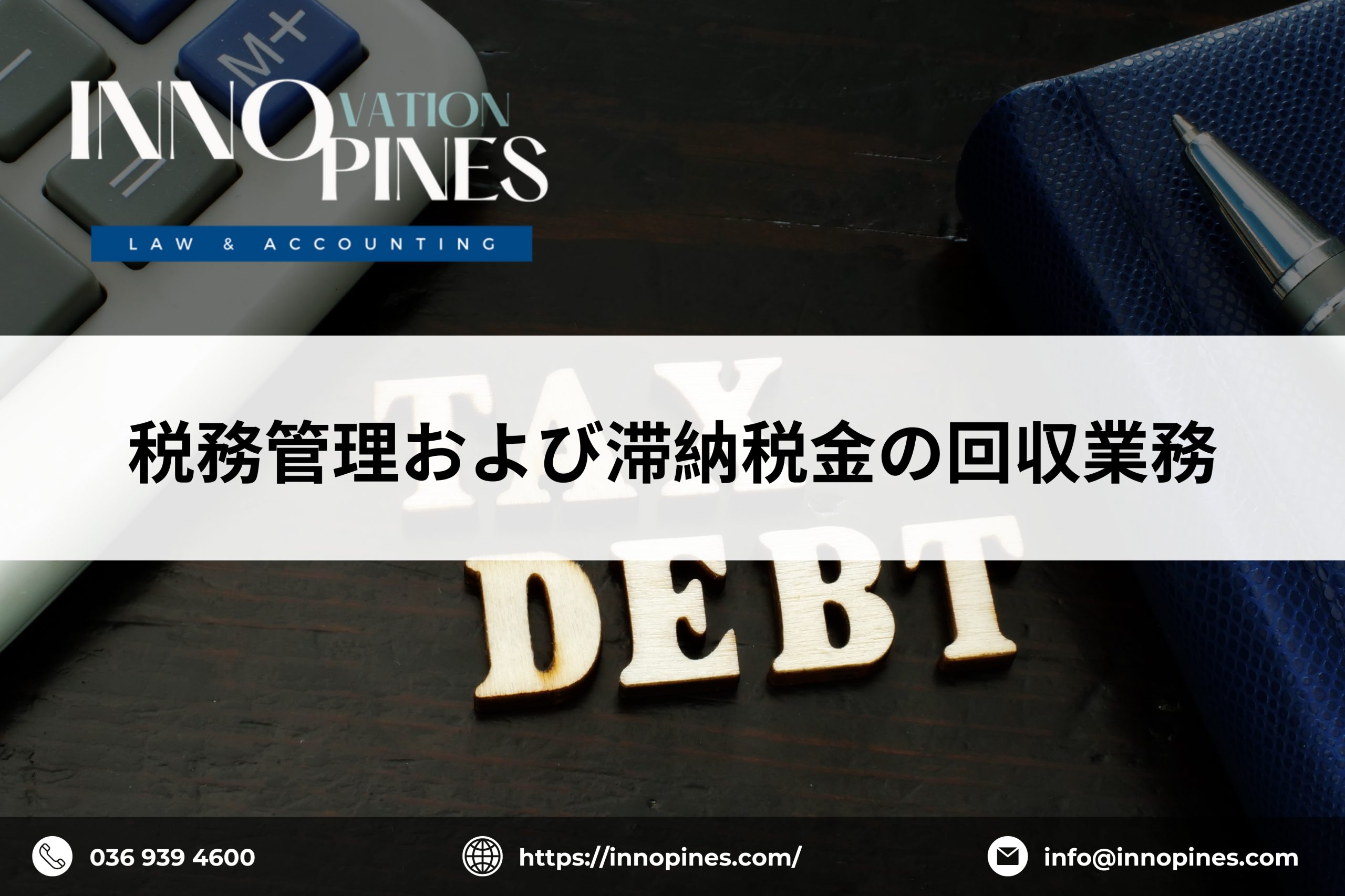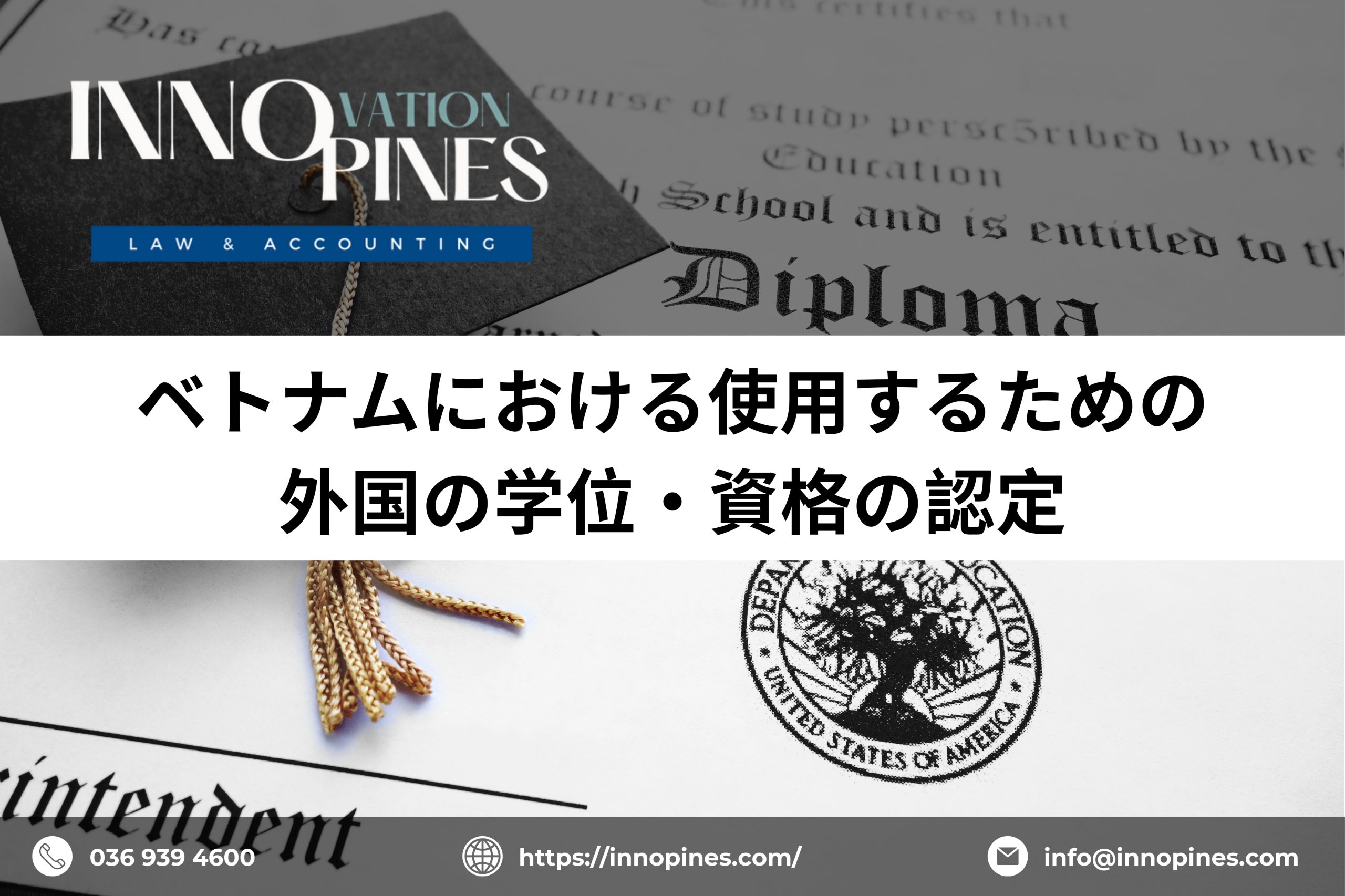I. 法的根拠
・商事仲裁法第5、16、18、19条
・2014年3月20日の政令第01/2014/NQ-HDTP号の第2,3、7条

II. 仲裁で紛争を解決する条件
1.紛争は関係者が仲裁合意がある場合、仲裁で解決されます。仲裁合意は紛争を起こす前、または後に確立されます。
2.仲裁合意に参加するの一方の当事者は亡くなったまたは行為能力の喪失の個人の場合、仲裁合意はその人の相続人または法定代理人に有効があります、関係者が他の合意がある場合を除きます。
3.仲裁合意に参加するの一方の当事者は活動が終了、破産、解散、新設、吸収、分割、分離され、または組織の形態を変更する組織の場合、仲裁合意はその組織の権、義務を受ける組織に有効があります、関係者が他の合意がある場合を除きます。
4.仲裁人の管轄下の分野に発生した紛争:
4.1.商業活動から発生した関係者の紛争。
4.2.関係者から発生し、少なくとも一方の当事者は商業活動を行っている紛争。
4.3.仲裁で解決することを法律が規定した関係者の他の紛争。
5.無効の場合ではない
無効の場合は次のように含みます:
5.1.仲裁人の管轄下の分野ではないが発生した紛争。
5.2.仲裁合意を確立する人は法律の規定により管轄がありません。
・法定代理人ではない、または合法的に権限を受けた人ではない、または合法的に権限を受けたが権限範囲に超えた人の場合。
・仲裁合意は管轄がない人から確立されたが、確立、実行する過程中、または訴訟仲裁中、仲裁合意を管轄がある人は合意を受けた、または知っていたが反対しない場合、その仲裁合意は無効ではありません。
5.3.仲裁合意を確立する人は民事法の規定により、民事行為能力がありません。
5.4.仲裁合意の形態は法律の規定に従いません。
5.5.一方の当事者は仲裁合意を確立する中にだまされ、脅迫され、強制され、その仲裁合意が無効の要求があります。
5.6.仲裁合意は法律の禁止事項に違反します。
III. 仲裁合意の形態
1.仲裁合意は契約における仲裁条項の形態、または個別の合意の形態により確立することができる。
2.仲裁合意は文書で確立されなければなりません。下記の合意の形態も文書で確立されたとみなされます:
2.1.テレグラム、ファックス、テレックス、電子メール及び法律の規定により他の形態で関係者の情報交換を通じて確立された合意。
2.2.文書で関係者の情報を交換することを通じて確立された合意。
2.3.弁護士、公証人、または権限がある組織が関係者の要求の通り、文書で記録された合意。
2.4.取引における、関係者は契約書、証憑、会社の定款またはその他の同様の書類のような仲裁合意を表す文書に参照することがあります。
2.5.一方の当事者が提案し、他方の当事者が否定していない合意の存在を表す嘆願書,自己弁護の交換を通じます。
3.一つの紛争の内容に対して、多くの仲裁合意が確立された場合、仲裁合意は適用価値がある期間とり最後に確立されます。
4.仲裁合意の内容に不明な点があり、多くの意味で理解できる場合、民事法を適用し、説明することができます。
5.合法的に仲裁合意を確立した取引、契約の中でその取引、契約から発生した権利、義務の譲渡がある場合、譲渡をする方及び譲渡を受ける方に対して、取引、契約における仲裁合意は有効があり、関係者は他の合意がある場合を除きます。
6.紛争の法律関係を集め、一つの訴訟で解決することは下記のような場合に実行されます:
6.1.関係者は紛争の法律関係を集め、一つの訴訟で解決することに同意します;
6.2.仲裁規則は紛争の法律関係を集め、一つの訴訟で解決することを許可します。
7.仲裁合意は完全で契約と独立です。契約を変化、延長、キャンセルすること、無効、または実行できない契約は仲裁合意を無効にすることができません。